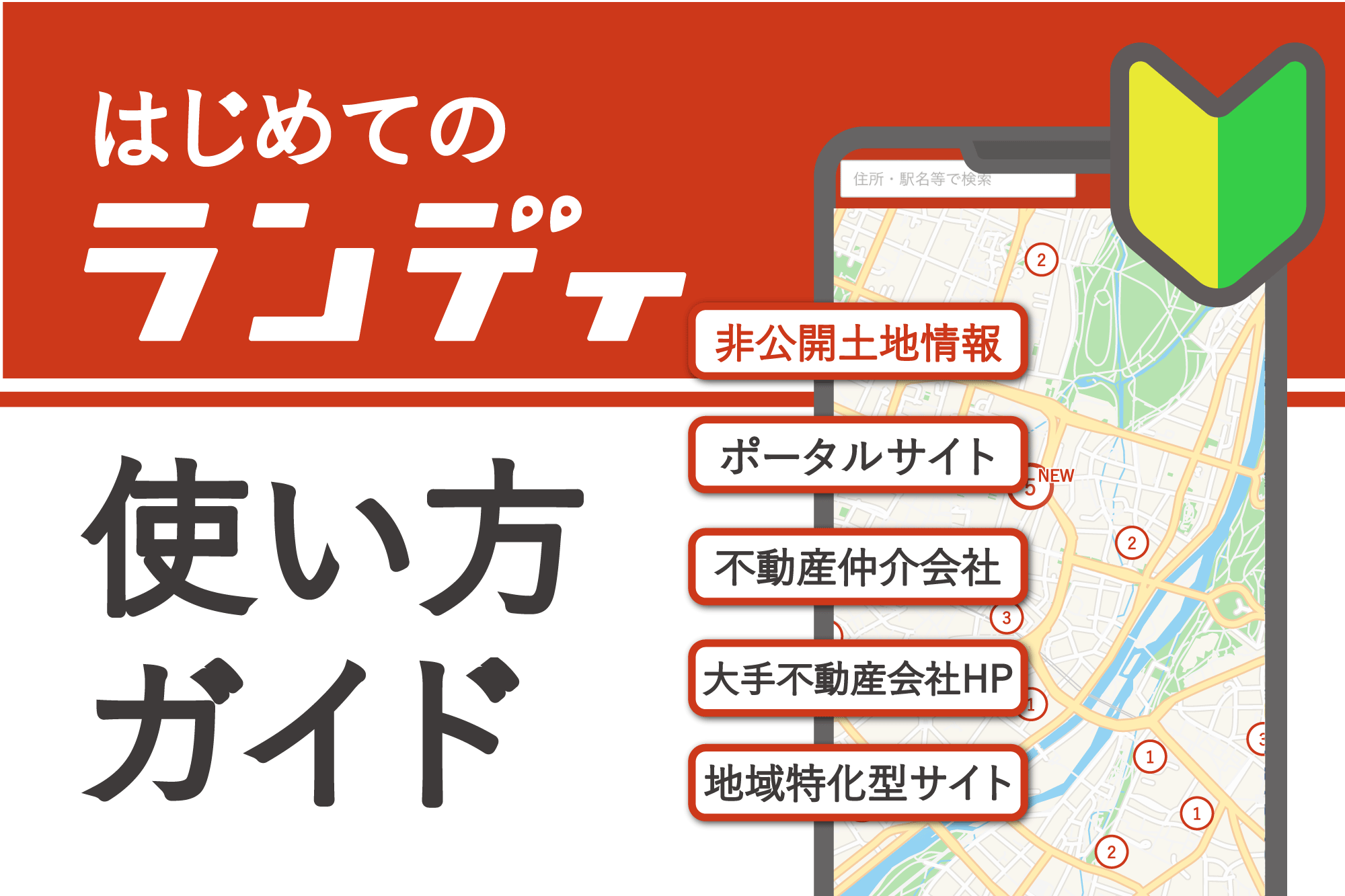ノウハウKNOW-HOW
建ぺい率・容積率とは?理想の家づくりに役立つ計算方法や緩和条件を解説
理想の家づくりを行うためには、建ぺい率や容積率を理解しておく必要があります。
建物の大きさを制限する数値なため、計算などが難しいイメージもありますが、それぞれ一つずつ理解すればそれほど難しくはありません。
この記事では、建ぺい率や容積率の概要や計算方法、緩和する条件や注意点などを分かりやすく解説します。家づくりに役立つ重要な知識のため、必ず押さえておきましょう。

建ぺい率が決められているのは、敷地内に適切な空地を設け、採光や通風などの住み心地や安全性の確保を図るためです。また、住居地域の建ぺい率は、30〜80%の範囲で設定されています。「自分の土地で自由に立てられないのはおかしい」と感じる方もいるでしょう。しかし、全員が建ぺい率100%の家を建てると「日当たりや風通しなど快適な住環」「防火や避難などの安全性」が確保できません。
建ぺい率の調べ方は、不動産会社やハウスメーカーが扱う土地であれば、チラシやWEBサイトに記載があります。もしくは、市区町村への問い合わせや行政のWEBサイトで公開されている都市計画図でも確認することができます。

延べ床面積は「建築物の各階の床面積の合計」を指します。1階が100㎡、2階が90㎡の場合は合計190㎡の延べ床面積です。同じ広さの土地でも容積率が高ければ建築可能な延べ床面積が増えるため、より部屋を広くしたり、部屋数を増やしたりできます。
容積率が決められているのは、住み心地や安全性の確保だけではなく、人口密度のコントロールをするためでもあります。容積率に制限がなければ「戸建住宅が並ぶ土地に高層マンションが建築され住み心地が悪くなる」ことや「人口増加による交通渋滞や電力消費、下水処理などへの負荷」が考えられるでしょう。
調べ方は建ぺい率と同じく、不動産会社やハウスメーカー、行政への問い合わせやWEBサイトで都市計画図を確認することができます。
例えば、建物面積50㎡、敷地面積100㎡の場合「50÷100✕100=50%」になります。また、建築可能な建物面積を算出したい場合の計算方法は「敷地面積✕建ぺい率=建築可能な建物面積」です。上記で使用した数字を使うと「100✕50%=50㎡」になります。
建ぺい率の異なる2つの土地にまたがる場合は、まずそれぞれの建物面積を計算後に合算し、次に2つの敷地面積を合計して割ると、それぞれの土地を合わせたときの建ぺい率が求められます。
たとえば、延べ床面積150㎡、敷地面積250㎡であれば「150÷250✕100=60%」になります。建築可能な延べ床面積を算出したい場合は「敷地面積✕容積率=建築可能な延べ床面積」です。上記で使用した数字を使うと「250✕60%=150㎡」になります。
また、容積率の異なる2つの土地にまたがる場合は、建ぺい率と同じく2つの建築面積を合算し、2つの敷地面積の合計で割ると算出可能です。
用途地域が設定されていることで「住宅地に危険物を扱う工場ができる」「戸建住宅が多い住宅地に高層マンションが建つ」などを防げます。
用途地域は、住宅系・商業系・工業系の3種類に大きく分けられます。それぞれ設定されている建ぺい率や容積率が異なるため、土地を購入する際は用途地域の種類を確認するようにしましょう。
住居系の用途地域それぞれの特徴や、設定されている建ぺい率・容積率は下記のとおりです。
※都市計画法や建築基準法で地域ごとに上限が定められているため、具体的な割合は市区町村の都市計画課で確認することができます。また、各自治体のWEBサイトからも調べることも可能です。
引用:国土交通省「みらいに向けたまちづくりのために-都市計画の土地利用計画制度の仕組み-」
特定行政庁の指定要件を満たす角地であれば「建ぺい率がプラス10%」、防火地域内・準防火地域内にある耐火建築物等の場合は「プラス10%」になります。
いずれの条件も満たすとプラス20%になり、定められた建ぺい率が80%の場合は100%の建ぺい率になるため、敷地面積を最大限活用することが可能です。
上手に活用することで、居住スペースを広くすることができるでしょう。
駐車場は、屋根のある駐車スペース(ビルトインガレージ)や駐輪スペースは延べ床面積に含まれますが、建築物の延べ床面積の「5分の1以内」は容積率から除外されます。また、地下室は住宅の延べ床面積合計の「3分の1以内」は容積率から除外されるという条件です。
建ぺい率や容積率の理解をより深められるため、ぜひご覧ください。
特に大手のメガバンクは厳しくなるため、注意しなければいけません。
融資や住宅ローンが組みにくい理由は、違法建築物に担保価値がないためです。購入前に不動産会社に相談し、確認をした上で購入するようにしましょう。
また、リフォームによる建ぺい率、容積率のオーバーも、売却が難しくなるため注意が必要です。しかし、建築時には合法であった「既存不適合建築物」であれば売却できる可能性があります。
ここでは、全ての自治体で共通する基準を持つ3つの制限と、自治体が基準を決める2つの制限を紹介します。
まずは共通する3つの制限です。
1.建築物の高さ制限(絶対高さ制限)
第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域、田園住居地域に適用されます。建築物の高さが10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはならないという制限です。
2.接道義務
都市計画区域内で建築する際、建築基準法上の道路(幅員4m以上)に「2m以上接した敷地(土地)」でないといけないという制限です。
3.斜線制限
道路境界線または、隣地境界線からの距離に応じて建築物の各部分の高さを制限することで、道路や隣地の採光、通風の確保は圧迫感を和らげるための制限です。
続いて、自治体が基準を決める制限を紹介します。
4.日影規制
中高層の建物が原因の日影を一定時間内に抑えることにより、日照環境を保護する目的の制限です。
5.高度地区指定
最低限守るべき建物の高度を指定し、住環境の保全や良好な町並みを守ることを目的とした制限です。
各規制には細かなルールや緩和条件があるため、気になる方は別途調べてみましょう。家を建てる際は、上記の規制をすべてクリアする必要があります。土地の購入前に建築会社に相談して規制をクリアした家づくりを行いましょう。
延べ床面積に含まれない部分
・玄関ポーチ
・条件内のロフト
・ベランダやバルコニー
建築面積に含まれない部分
・突き出ている部分が1m以下の軒や庇
・物置
・小屋
建ぺい率や容積率の緩和条件と合わせて覚えておくと、家づくりの際に役立つでしょう。

候補に挙げた土地の用途地域や建ぺい率、容積率を調べることはもちろん、その他規制にも気を配る必要があります。とはいえ、全てを正確に把握することは難しいでしょう。
土地を購入して注文住宅の家づくりを検討している中で、建ぺい率や容積率、各種規制に関して不安がある方はランディ加盟店への来場がおすすめです。土地探しから家づくりまでワンストップで相談できます。
この記事では、建ぺい率や容積率の概要や計算方法、緩和する条件や注意点などを分かりやすく解説します。家づくりに役立つ重要な知識のため、必ず押さえておきましょう。
- 建ぺい率と容積率とは?概要と調べ方
- 建ぺい率と容積率の計算方法と計算事例
- 用途地域による建ぺい率・容積率
- 建ぺい率や容積率が緩和される条件
- 建ぺい率や容積率に関する注意点
- 建ぺい率と容積率を理解して理想の家を建てよう
建ぺい率と容積率とは?概要と調べ方
建ぺい率と容積率を理解するためには、まずは概要を知り全体像を掴むことが大切です。それぞれ詳しい内容や重要性、調べ方などを解説します。建ぺい率とは?

建ぺい率が決められているのは、敷地内に適切な空地を設け、採光や通風などの住み心地や安全性の確保を図るためです。また、住居地域の建ぺい率は、30〜80%の範囲で設定されています。「自分の土地で自由に立てられないのはおかしい」と感じる方もいるでしょう。しかし、全員が建ぺい率100%の家を建てると「日当たりや風通しなど快適な住環」「防火や避難などの安全性」が確保できません。
建ぺい率の調べ方は、不動産会社やハウスメーカーが扱う土地であれば、チラシやWEBサイトに記載があります。もしくは、市区町村への問い合わせや行政のWEBサイトで公開されている都市計画図でも確認することができます。
容積率とは?

延べ床面積は「建築物の各階の床面積の合計」を指します。1階が100㎡、2階が90㎡の場合は合計190㎡の延べ床面積です。同じ広さの土地でも容積率が高ければ建築可能な延べ床面積が増えるため、より部屋を広くしたり、部屋数を増やしたりできます。
容積率が決められているのは、住み心地や安全性の確保だけではなく、人口密度のコントロールをするためでもあります。容積率に制限がなければ「戸建住宅が並ぶ土地に高層マンションが建築され住み心地が悪くなる」ことや「人口増加による交通渋滞や電力消費、下水処理などへの負荷」が考えられるでしょう。
調べ方は建ぺい率と同じく、不動産会社やハウスメーカー、行政への問い合わせやWEBサイトで都市計画図を確認することができます。
建ぺい率と容積率の計算方法と計算事例
土地の建ぺい率や容積率を調べられても、正しく計算できなければいけません。ここでは、事例を交えながらそれぞれの計算方法を解説します。建ぺい率の計算方法と計算事例
建ぺい率の計算方法は「建ぺい率=建物面積÷敷地面積×100」です。例えば、建物面積50㎡、敷地面積100㎡の場合「50÷100✕100=50%」になります。また、建築可能な建物面積を算出したい場合の計算方法は「敷地面積✕建ぺい率=建築可能な建物面積」です。上記で使用した数字を使うと「100✕50%=50㎡」になります。
建ぺい率の異なる2つの土地にまたがる場合は、まずそれぞれの建物面積を計算後に合算し、次に2つの敷地面積を合計して割ると、それぞれの土地を合わせたときの建ぺい率が求められます。
容積率の計算方法と計算事例
容積率の計算方法は「容積率=延べ床面積÷敷地面積×100」です。たとえば、延べ床面積150㎡、敷地面積250㎡であれば「150÷250✕100=60%」になります。建築可能な延べ床面積を算出したい場合は「敷地面積✕容積率=建築可能な延べ床面積」です。上記で使用した数字を使うと「250✕60%=150㎡」になります。
また、容積率の異なる2つの土地にまたがる場合は、建ぺい率と同じく2つの建築面積を合算し、2つの敷地面積の合計で割ると算出可能です。
用途地域による建ぺい率・容積率
地域ごとの環境を整えるための用途地域の概要と、用途地域ごとの建ぺい率・容積率を解説します。用途地域とは?
用途地域とは、地域ごとに合理的な規制を行い、住みやすい環境を作るために設定されているものです。用途地域が設定されていることで「住宅地に危険物を扱う工場ができる」「戸建住宅が多い住宅地に高層マンションが建つ」などを防げます。
用途地域は、住宅系・商業系・工業系の3種類に大きく分けられます。それぞれ設定されている建ぺい率や容積率が異なるため、土地を購入する際は用途地域の種類を確認するようにしましょう。
用途地域による建ぺい率・容積率
用途地域の種類を確認すれば、町並みや地域の特徴が大まかに分かります。住居系の用途地域それぞれの特徴や、設定されている建ぺい率・容積率は下記のとおりです。
※都市計画法や建築基準法で地域ごとに上限が定められているため、具体的な割合は市区町村の都市計画課で確認することができます。また、各自治体のWEBサイトからも調べることも可能です。
| 用途地域 | 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅が主な地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
| 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅や小規模店舗、小中学校が主な地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
| 田園住居地域 | 農業と調和した低層住宅を建てることは認められる地域 | 30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅が主な地域 | 30・40・50・60 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅や一定の店舗や事務所が主な地域 | 30・40・50・60 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第一種住居地域 | 住宅環境保護を目的とした地域。大型店舗や事務所の建築も可能 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 第二種住居地域 | 第一種住居地域の範囲に加え、パチンコ店やカラオケ店等も建築可能な地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
| 準住居地域 | 第二種住居地域の範囲に加え、営業用倉庫や小規模工場などの建築も可能な地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |
建ぺい率や容積率が緩和される条件
建ぺい率や容積率は緩和される条件があります。条件を把握しておくと、居住スペースを確保しつつ、利便性の高い家づくりができるため押さえておきましょう。建ぺい率の条件
建ぺい率緩和の条件は、「特定行政庁の指定要件を満たす角地」「防火地域内・準防火地域内にある耐火建築物等」の2つです。特定行政庁の指定要件を満たす角地であれば「建ぺい率がプラス10%」、防火地域内・準防火地域内にある耐火建築物等の場合は「プラス10%」になります。
いずれの条件も満たすとプラス20%になり、定められた建ぺい率が80%の場合は100%の建ぺい率になるため、敷地面積を最大限活用することが可能です。
容積率の条件
容積率緩和の条件は、駐車場や地下室に関する特例を紹介します。上手に活用することで、居住スペースを広くすることができるでしょう。
駐車場は、屋根のある駐車スペース(ビルトインガレージ)や駐輪スペースは延べ床面積に含まれますが、建築物の延べ床面積の「5分の1以内」は容積率から除外されます。また、地下室は住宅の延べ床面積合計の「3分の1以内」は容積率から除外されるという条件です。
建ぺい率や容積率に関する注意点
建ぺい率や容積率には、リスクを回避できたり家づくりに役立てたりできる、覚えておきたい注意点があります。建ぺい率や容積率の理解をより深められるため、ぜひご覧ください。
建ぺい率・容積率がオーバーしている建築物は売却しづらい?
建ぺい率や容積率を守っていない建築物は違法建築物になるため、銀行の融資や住宅ローンが組みにくくなります。特に大手のメガバンクは厳しくなるため、注意しなければいけません。
融資や住宅ローンが組みにくい理由は、違法建築物に担保価値がないためです。購入前に不動産会社に相談し、確認をした上で購入するようにしましょう。
また、リフォームによる建ぺい率、容積率のオーバーも、売却が難しくなるため注意が必要です。しかし、建築時には合法であった「既存不適合建築物」であれば売却できる可能性があります。
<建ぺい率や容積率以外にも建築制限がある>
家を建築する際の制限は、建ぺい率や容積率だけではありません。ここでは、全ての自治体で共通する基準を持つ3つの制限と、自治体が基準を決める2つの制限を紹介します。
まずは共通する3つの制限です。
1.建築物の高さ制限(絶対高さ制限)
第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域、田園住居地域に適用されます。建築物の高さが10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはならないという制限です。
2.接道義務
都市計画区域内で建築する際、建築基準法上の道路(幅員4m以上)に「2m以上接した敷地(土地)」でないといけないという制限です。
3.斜線制限
道路境界線または、隣地境界線からの距離に応じて建築物の各部分の高さを制限することで、道路や隣地の採光、通風の確保は圧迫感を和らげるための制限です。
続いて、自治体が基準を決める制限を紹介します。
4.日影規制
中高層の建物が原因の日影を一定時間内に抑えることにより、日照環境を保護する目的の制限です。
5.高度地区指定
最低限守るべき建物の高度を指定し、住環境の保全や良好な町並みを守ることを目的とした制限です。
各規制には細かなルールや緩和条件があるため、気になる方は別途調べてみましょう。家を建てる際は、上記の規制をすべてクリアする必要があります。土地の購入前に建築会社に相談して規制をクリアした家づくりを行いましょう。
<延べ床面積や建築面積に含まれない部分がある>
延べ床面積や建築面積に含まれない部分を把握しておけば、居住スペースを広く設計できます。それぞれの含まれない部分は以下のとおりです。延べ床面積に含まれない部分
・玄関ポーチ
・条件内のロフト
・ベランダやバルコニー
建築面積に含まれない部分
・突き出ている部分が1m以下の軒や庇
・物置
・小屋
建ぺい率や容積率の緩和条件と合わせて覚えておくと、家づくりの際に役立つでしょう。
建ぺい率と容積率を理解して理想の家を建てよう

候補に挙げた土地の用途地域や建ぺい率、容積率を調べることはもちろん、その他規制にも気を配る必要があります。とはいえ、全てを正確に把握することは難しいでしょう。
土地を購入して注文住宅の家づくりを検討している中で、建ぺい率や容積率、各種規制に関して不安がある方はランディ加盟店への来場がおすすめです。土地探しから家づくりまでワンストップで相談できます。